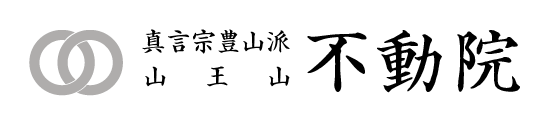当山の縁起
むかし人皇第五十二代嵯峨天皇の御代(弘仁九年・西暦八一八年)に国中に疫病が流行し、このために命を失うものが数知れぬ程であった。
天皇はこの悲惨な有様を見聞かれまして大変に驚き憐れまれ、昼夜御心を痛められておりました。
丁度その頃、紀伊国(今の和歌山県)高野山を開かれた弘法大師に「疫病退散、天下安全のために般若心経の秘鍵を製作するように」との詔りがあり、その結願がまだ来ないうちに、さしもの悪い病業の流行も忽ち止んで、世の中は暗い闇夜から、日の光りまばゆい明るさを取り戻すことが出来ました。
この時、大師は心中に深く祈願され、自ら大聖不動明王の尊躰を八躯彫刻され洛陽(京都)の八方に安置いたしまして、国家安全の秘法を修せられました。
その后、百二十年程経た人皇第六十一代朱雀天皇の天慶二年(九三九年)に桓武天皇の子孫で、坂東下總国に相馬小次郎平将門という猛将がおり、野心を抱いて新都を築き、自ら親王と称え、横暴目に余るものがありました。ここに広沢の遍照寺僧正寛朝は勅命を蒙って北山高尾山の護摩堂本尊、弘法大師彫刻の不動明王を護持し、下總国に下り、利根の大川を隔て、成田の郷に精舎(今の新勝寺)を建立し、将門調伏の秘法を修せられました。時を同じくして、苗裔平貞盛は藤原秀郷と共に征伐の兵を起し、この尊像に祈誓して、「帰命頂礼大聖不動明王の加被力を以て速やかに逆賊を退治なさしめ給え」と祈願されましたところ、その利益があらわれ、終に将門の猛威を討ち滅ぼすことが出来ました。
この時、寛朝僧正は平生護持していた大師彫刻の、不動明王すなわち成田の不動尊と同木同作の明王を、葛飾八幡の辺り、菅野の里に安置したのが今の本尊であると伝えられて居ります。
* * * * * * * *
それから凡そ八百余年の年月を経て、天正十八年(一五九〇年)に豊臣太閣秀吉が坂東に下向した時、 深くこの本尊に祈念され三年程経た文禄二年の秋に秀頼公が誕生した後に、今の不動院境内及び寺領を賜わりました。
その后も時の公儀から御願があって、寺領を賜わった事もあり、叉戸田左門一昭、成瀬伊豆守、小池猪兵衛、鈴本茂兵衛、藤村四郎兵衛、榎本九郎兵衛、會根勘六等連名の御寄附書もあり、また享保の頃、大岡越前守の御勤役中にもいろいろの儀があったということや、宝物、諸記録が相当に蔵されていたというようなことが俚語に伝えられておりますが、何しても過去三度の祝融の災いに罹って、旧記録が焼失し、以上のことが忠実に拠い詳らかにされないのが誠に残念であります。
[弘化四年(一八四七年)下総国葛飾郡菅野不動院本尊不動明王縁起]より


不動院の仏さま
本尊
大聖不動明王(立像)


右脇尊
大聖不動明王(座像)


左脇尊
聖観世音菩薩


不動院 年中行事
新春初護摩供
初不動大護摩供
節分祭豆まき
春彼岸
花まつり
大施餓鬼会
正五九大護摩供
新盆合同供養会
盂蘭盆合同供養会
秋彼岸
納不動
節分祭豆まき
節分祭は新しい季節を迎えるにあたり邪気や厄難を祓う大切な行事です。大聖不動明王の御宝前にて大護摩祈願法要を厳修し、所願の成就を謹んでお祈りいたします。


大施餓鬼会
大施餓鬼会は、餓鬼道に堕ちて苦しんでいる霊を供養することにより得た功徳を、ご先祖さまをはじめ、私たちの命を支えているあらゆる生き物の霊(三界萬霊)に巡らせる、感謝のための総供養です。